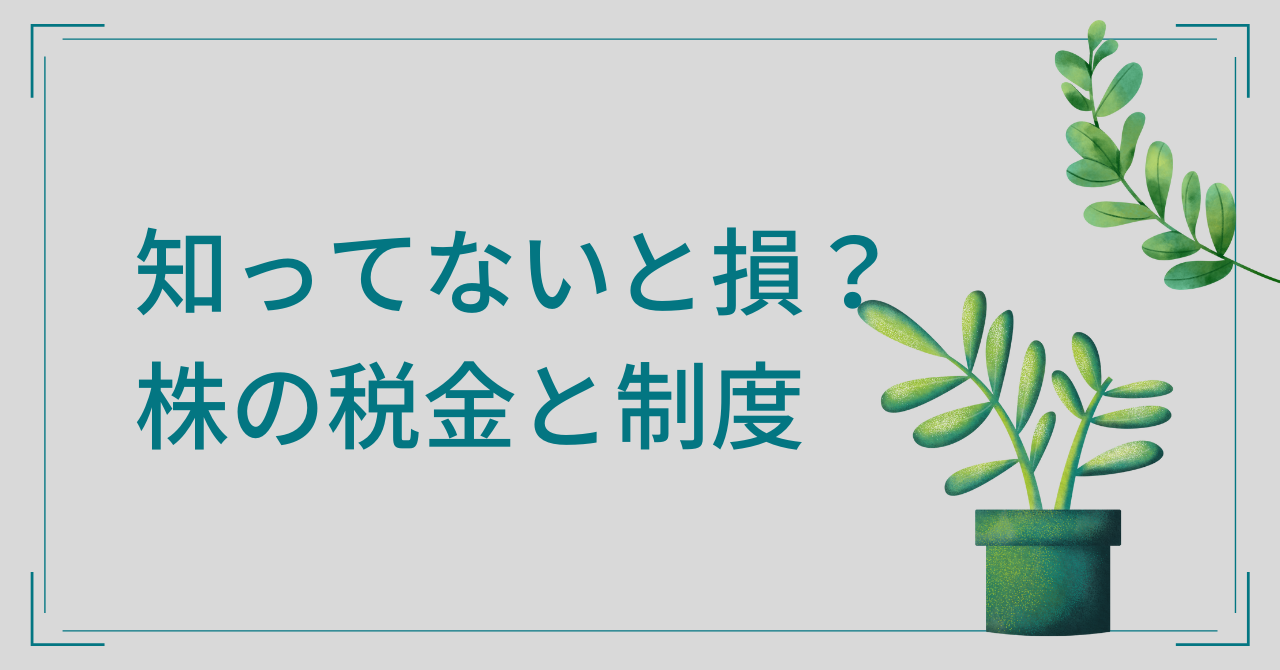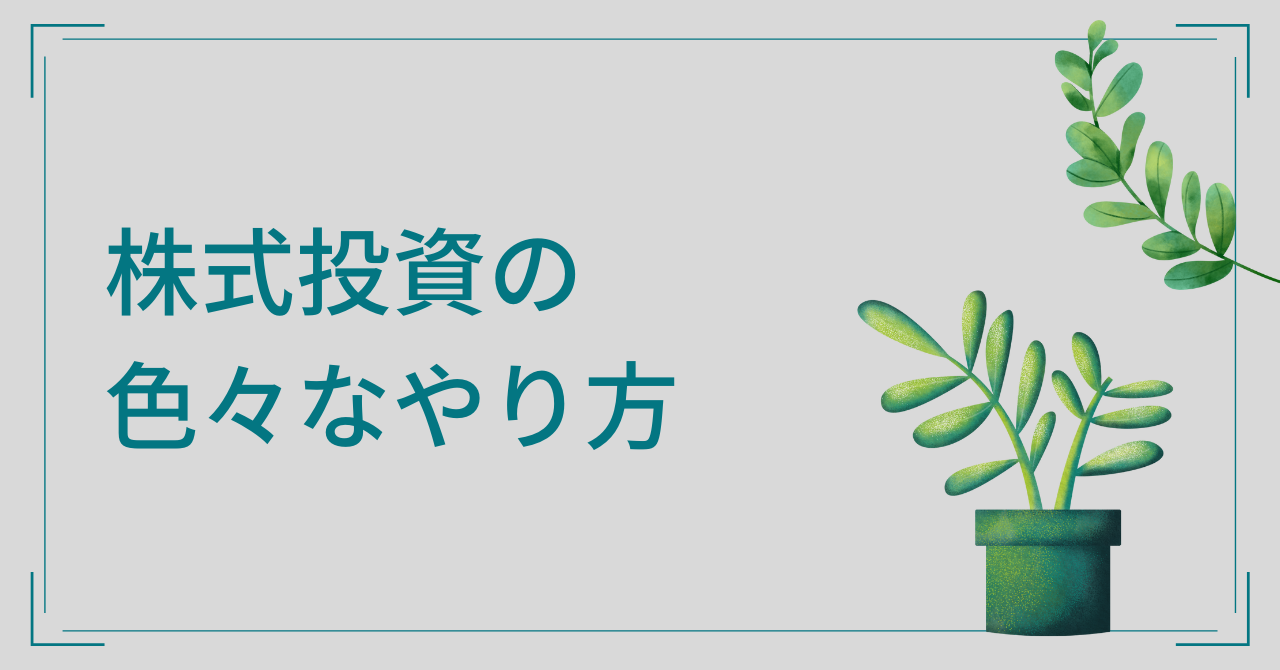こんにちは、たちば7です。今回は株にかかる税金とお得な制度について事もお話ししたいと思います。
株の税金
配当金と譲渡益
最初に株式投資で発生する税金は①会社から株主への配当金にかかる配当課税②売却した株式に発生する譲渡益(売却益)にかかる譲渡課税となります。
それぞれにかかる税金は同じで税率は20.315%です。(内訳①所得税15%②住民税5%③復興特別所得税0.315%)とだいたい2割は税金で取られることになります。
補足として説明しますが、証券口座には一般口座と特定口座の2つあります。簡単に話しをすると特定口座の方は税金を天引きして入金してくれるので自分で確定申告を行わなくて良いので楽です。ちなみに私も特定口座にしています。
課税される所得金額 税率 所得金額税率控除額
- 1,000円 ~ 1,949,000円 5% なし
- 1,950,000円 ~ 3,299,000円 10% 97,500円
- 3,300,000円 ~ 6,949,000円まで 20% 427,500円
- 6,950,000円 ~ 8,999,000円まで 23% 636,000円
- 9,000,000円 ~ 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
- 18,000,000円 ~ 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
- 40,000,000円 以上 45% 4,796,000円
上記に表しているのが給与所得での税率と控除額になります。例えば、株式投資で900万を稼いだら・・・900万の約2割で約180万が税金になりますが給与所得の場合は900万に33%なら297万で控除が約15万として引くと282万になり、約100万近くの差になるのです。かなり差があると思います。
これは給与所得が累進課税を採用しているからです、簡単にいうとたくさん稼ぐほど税率があがるということです。補足としてかなり所得が高い人は色々な控除がなくなっていきますので、なかなか厳しいと私は思います。
税金の制度
次にはお得な税金の制度についてお話ししたいと思います、私自身も活用しているのでぜひ聞いてください。
NISAと積立NISA
さてNISAはイギリスのISAをモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)といいます。NISA と積立NISA は、非課税口座内で、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり分かりやすくいいますと上記で説明したような株式投資での税金がこの2つの制度を活用すると税金がかからなくなるのです。
- NISAは2014年1月から始まりました。毎年120万円(最大5年間で)の非課税投資枠が設定され、国内株式・外国株式・投資信託が非課税対象となります。
- 積立NISAは2018年1月から始まりました。特に少額からの長期・積立・分散投資が目的。購入できる金額はNISAと違い年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、期間は20年間で、購入可能な商品は、国が定めた基準を満たした投資信託に限られています。
NISAと積立NISAの違いは上記の部分です。期間が違う、毎年の税金がかからない額が違う、購入できる金融商品が違うということです。この制度を活用したい方はまずどんな目的で資産を増やしたのかともし毎月一定額を入れるとしたらNISAは毎月10万円、積立NISAは毎月約3.3万円になります。日々の生活もあると思いますのでそのあたりも考えて下さい。
iDeCo
iDeCoとは、公的年金とは別に自らが加入する私的年金制度の1つです。
特徴として、掛け金は自分で決められます、NISAと積立NISAと同じく運用中に得られた利益は非課税になり、積み立てた金額で所得税・住民税が軽減されます。受取時は年金・一時金どちらでも選択可であり一定額までが非課税ですが60歳まで引き出せないのがデメリットです。
- 第1号被保険者 自営業者など 月額6万8千円
- 第2号被保険者 会社員 月額2万3千円(企業年金なし)
- 〃 会社員 月額1万2千円(企業年金あり)
- 〃 会社員 月額2万円(企業年金あり、企業型DCのみあり)
- 〃 公務員など 月額1万2千円
- 第3号被保険者 専業主婦 月額2万3千円
掛け金の上限は上記に書いてある通りなのでお間違いなく。
以上で株式投資の税金と制度のメリットについて話させていただきましたが知っといて損はないと思います、このブログで興味をもって活用したいと思う方がいましたら幸いです。それでは最後までお読みいただき有り難うございました。